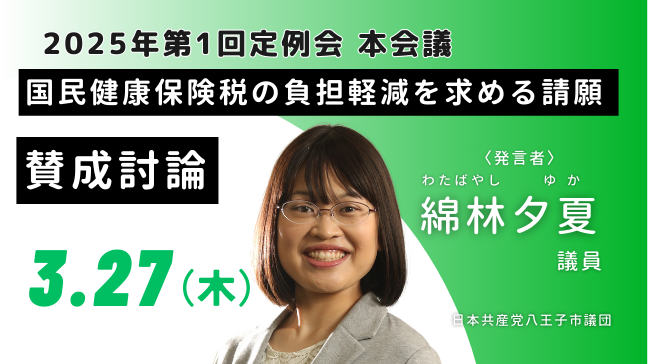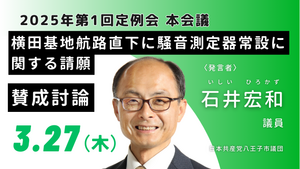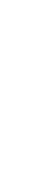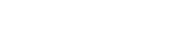2025年第1回定例会本会議|国民健康保険税の負担軽減を求める請願 賛成討論|2025年3月27日 わたばやしゆか
それでは、請願第6号「国民健康保険税の負担軽減を求める請願」に賛成の立場から討論を行います。
請願事項の第一 は、法定外繰入金の削減ではなく、繰入金を増やして加入者の負担軽減のために国民健康保険税の値下げを求めることについてです。
本市の国保税は、都道府県化が開始された2018年度以降、7年連続の国民健康保険税の改定・値上げを行ってきました。その結果、多摩26市の中でも均等割額・所得割率ともに最も高い税の水準になっております。また年収400万円4人家族の試算でみると全国1786自治体のうち83番目に高い自治体であることが明らかになっています。
「八王子市国民健康保険事業概要」によると、滞納処分による差し押さえ件数は2019年度が254件であったのに対し、2022年度では3047件、2023年度では9015件と激増していることからも市民生活の厳しさは明らかです。
昨年3月に発表された全日本民主医療機関連合会の調査によれば、経済的な理由で受診を控えた末に、手遅れ状態となり死亡した事例が22の都道府県で48件報告されています。そのうち受診前に無保険だった事例は22件、全体の46%でした。また、負債を抱えている事例は20件で、滞納している税や公共料金の中では国民健康保険税の滞納が最も多く20件でした。
無保険に至る経緯には、「被用者保険加入者が退職・解雇後、経済的に国保料が支払えない」「非正規雇用者の失業」「借金返済により国保料が支払えない」「生活保護廃止後、国保加入手続きがされない」などが挙げられています。いずれにせよ、保険料を支払う経済的な余裕がない困窮者が無保険となっている実態が見えてきます。
国民健康保険税の負担が、本市の国保加入世帯の生活を苦しくしているだけでなく、高すぎる国保税により無保険状態に陥り、受診をあきらめさせてしまうことが調査からも明らかとなっています。国保加入者の負担軽減は、国民皆保険制度を守るためにも必要なことです。
しかし今回、市はこれまで行ってきた一般会計からの法定外繰入金をなくして、結果的に国保加入者に負担を強いる8年連続の値上げを進めようとしています。
東京都は、2023年度から2024年度にかけての医療給付費の伸びを実際よりも大きく見込んだことにより、生じた約235億円もの余剰金を活用し、新年度の国民健康保険事業費納付金を減額し、本市は前年度比で13億9600万円減額となりました。しかし新年度は今年度と比較して所得割0.14%増、均等割400円増と8年連続の値上げ案が示されています。
今回の改定で、年金収入の方や40歳未満の方は値下げになり、被保険者の4分の3の世帯がその恩恵を受けるというものです。しかし依然として収入に占める国民健康保険税の割合は1割近い水準で、重すぎる負担となっています。
さらに、残りの4分の1の世帯の方は値上げとなります。今回値上げになる階層・世帯を値上げせず据え置きとした場合、1億円が必要との試算が示されました。令和5年度の決算では法定外繰入金6億9700万円でした。そのうちの約7分の1の繰入を行えば値上げを止めることができたわけです。繰入金をゼロにすることを優先する市の姿勢は問題です。
都内自治体で、法定外繰入金を1円も計上していない自治体は、本市の他には1区2町村のみで、多摩26市の中では本市が初めてとなります。
2018年度から国民健康保険制度が都道府県単位化されてから、本市では東京都の示す標準保険税率に近づけるために値上げをし続けてきました。標準保険料率に合わせることで繰入金をゼロにできるとして値上げを続けてきましたが、2024年度は都の標準保険料率に追いついても足りず、予算では8億円の繰入金を計上することとなりました。2025年度は東京都に納める納付金が下がったことで繰入金をゼロにすることができたと市は説明していますが、24年度のように標準保険料率に合わせても足りないという事態は十分起こりえます。繰入金をゼロにすることを継続すれば、待っているのは更なる国保税の値上げです。本請願が求めているように、法定外繰入金の削減ではなくむしろ増やして国民健康保険税の値下げを行うことは、社会保障制度の実行を担う自治体に求められている責任であります。
請願事項の第二 は、子どもの均等割軽減を市独自で行うとともに国に対して均等割の廃止を求めることについてです。
国民健康保険税の「均等割」は、加入者だけに課税される他の被用者保険とは異なり、被保険者の世帯全員に課税され、多子世帯ほど負担が重くなっています。
2022年度から実施されている子どもにかかる均等割保険料軽減措置は、対象となる子どもの範囲が未就学児と限定され、その軽減額も5割と十分なものではありません。すでに多摩地域では武蔵村山市、昭島市、清瀬市で子どもの均等割の独自軽減策を行っています。全国に目を向けますと、岩手県宮古市では2019年度から18歳以下の子どもの均等割を全額免除しており、名古屋市では、被保険者全員の均等割を2023年度から一律5%軽減しています。
子どもの均等割軽減は、本市が掲げる「将来の八王子を支える人財を育てる取組み」と合致するものであると考えます。
2023年12月の本市議会定例会において、「国民健康保険制度改革後の新たな構造的問題に関する意見書」が全会一致で可決されました。現在の国保制度が被保険者に過大な負担を強いる制度になっていることは誰もが認めるものです。全国知事会や全国市長会議では、国に対し、国庫負担割合の引き上げ、財政基盤強化のために財政支援とともに、子どもにかかる均等割保険料軽減措置について財政確保と対象年齢や軽減割合を拡大することを要望しています。
子どもの均等割軽減策を市独自で行うこととともに、国に対し均等割の廃止を求めることは、国民健康保険税の構造的な問題に光を当てる市民の切実な願いであります。
厚生労働省は都道府県化実施後も、「一般会計の繰入は自治体の判断でできる」「生活困窮者への自治体独自の軽減は問題ない」との見解を示しています。市は、法定外繰入金をゼロにすることによって保険努力者支援制度による国や都からのインセンティブを得られ、市民に還元できるとしています。しかし、インセンティブほしさに繰入れ解消にともなう国民健康保険税の値上げをし続けることは、社会保障の応能負担の原則をゆがめ、被保険者の税負担を際限なく強いることとなり、市民の利益にはなり得ません。また、子どもの均等割軽減のために独自の軽減策を講じることで、給付金が減らされるというペナルティがつくという仕組みも問題です。こうしたインセンティブやペナルティといった、自治体の判断で本来できるはずの国保加入者への負担軽減策を阻害するような国のやり方は、地方自治の原則をねじ曲げるものであり問題だということもこの場で指摘したいと思います。
本請願の各項目が、誰もが必要な医療を受けられる国民皆保険制度を守り維持する上でも必要不可欠なことであり、市民の切実な願いであることを申し上げ、賛成の討論といたします。
【録画中継】令和7年第1回定例会 3月27日 本会議 請願第6号 国民健康保険税の負担軽減を求める請願
※ わたばやしゆか議員の賛成討論は(11:31)(残り12:20)のあたりです