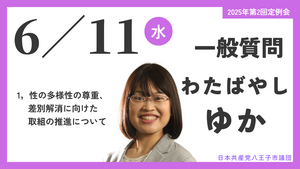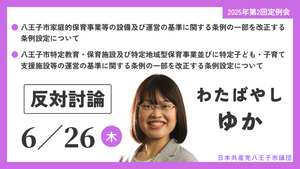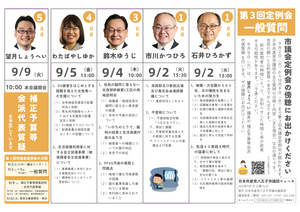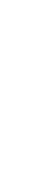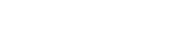2025年第2回定例会本会議|一般質問|2025年6月11日 わたばやしゆか
日本共産党八王子市議会議員団のわたばやしゆかです。
発言通告にもとづき、一般質問を行います。
今月6月はプライド月間として、日本やアメリカなど世界各地でLGBTQ+の権利を啓発する活動・イベントが実施されています。先日8日には、渋谷の代々木公園で、LGBTQ+(性的少数者)が自分らしく生きられる社会の実現をアピールするイベント「東京プライド2025」が開催されました。
このことにちなみ、今回、私は、
性の多様性の尊重、差別解消にむけた取組みの推進について
取り上げていきたいと思います。
本年の予算総括質疑でも確認をしてまいりました、
(1) 東京都パートナーシップ宣誓制度の活用・連携について
伺います。
本市では、東京都のパートナーシップ宣誓制度を、市営住宅入居、霊園申込、有料老人ホームやサービスつき高齢者住宅への入居、住宅セーフティネット制度における家賃低廉化補助住宅への入居申し込み、以上4業務において導入しています。また、業務の更なる掘り起こしをし、拡大を図っていくという市の考えもこの間の議論の中で示されてきました。
今回は、他の業務や制度への活用の拡大はどうなっているのか、職員の福利厚生制度と災害弔慰金の支給に着目して確認していきたいと思います。
ア、 職員の福利厚生制度への活用について
なぜ私が職員の福利厚生制度への活用について着目したのかと言いますと、東京都では、パートナーシップ宣誓制度の創設と合わせて、条例改正されていたのが、職員の福利厚生制度にかかわる条例であったからです。
東京都では、2022年第2回定例会において、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例が可決され、パートナーシップ宣誓制度が導入、同年11月1日より施行されました。同年の第3回定例会において、①職員の給与に関する条例、②旅費に関する条例、③勤務時間・休日・休暇に関する条例、④育児休業に関する条例、⑤退職手当に関する条例について、条例の施行を踏まえて改正が行われました。
また、東京都のパートナーシップ宣誓制度創設後に、市でパートナーシップ制度を創設した自治体は、26市の中で、町田市、日野市、調布市、三鷹市の4市ありますが、この4市とも、市のパートナーシップ制度の導入に合わせて、先ほど示した職員の福利厚生制度に関する5つの条例の改正を行っています。また、独自のパートナーシップ制度のない狛江市では、2023年第1回定例会において、職員の給与など、東京都パートナーシップ宣誓制度の施行に伴う関係条例の整備に関する条例が可決されています。
【Q】本市においては、職員の福利厚生の制度に関して、東京都パートナーシップ宣誓制度の施行に伴う条例の改正は行っていませんが、東京都パートナーシップ宣誓制度を結んだ職員に対しては、この5市と同様の対応がされているのかどうか、伺います。
【A】申し出の内容を踏まえて、適切に対応しているところです。
ここで、退職手当について掘り下げていきたいと思います。
職員が退職した場合に、退職手当は当人に支払われますが、職員が亡くなった場合には遺族に対して退職手当が支払われます。死亡退職金といいます。
死亡退職金を支払うことは、亡くなった労働者の功労の対価とすることや、遺族の生活の保障を目的としています。
退職手当(死亡退職金)を、規定により遺族の受け取る順位を定めている場合、死亡退職金は相続財産とは見なさず、遺族固有の権利と解する判例が通例となっているようです。とくに定めのない場合には、死亡した労働者の退職金の受取人は、民法で定められている法定相続人が受け取るものとしていますが、本市の退職手当に関する条例においては、受け取れる人について順位をもうけていることから、規定の順位によって一番上の順位に該当する者が遺族の固有の権利として受け取る、ということになるかと思います。
先ほど、「申し出の内容を踏まえて、適切に対応する」とのお答えがありました。
【Q】条例に明記はなくとも、退職手当の受取人順位の第一位から同性パートナーの方が排除されないように、個別の事情をふまえながら、市は対応していく、ということと受け止めましたが、その認識で良いのか、確認したいと思います。本市においても、東京都パートナーシップ宣誓制度を結んでいて、同居し、かつ生計を一にしていた方については、退職手当の受取人順位の第一位から除かれないよう対応していくということなのか、伺います。
【A】支給順位のある制度では、同性パートナーの方を支給対象に含めることで、その他の親族などへの影響が出てくる可能性がありますので、申し出の内容を踏まえて慎重に判断いたします。
遺族の固有の権利として、条例の規定にそって受取人の順位が決まるのであるのなら、同居して生計を一にしていた同性パートナーの方は、配偶者と同じ取り扱いがされるべきと考えます。受取人順位の第一位から同性パートナーの方が排除されることがないよう、対応をお願いいたしします。
イ、 災害弔慰金の支給への活用について
災害弔慰金とは、災害により死亡した者の遺族に対して、死亡者一人あたり500万円を超えない範囲内で支給される制度です。昭和48年に災害弔慰金の支給等に関する法律が制定されました。支給する主体は市町村自治体で、それぞれ条例を定め、対象の住民に支給します。
東京都パートナーシップ宣誓制度に関するホームページを確認したところ、災害弔慰金の支給について、同性パートナーシップの方も配偶者と同様の取り扱いをすると、パートナーシップ宣誓制度受理証明書活用一覧の調査に回答している自治体は、23区では9区、26市には4市ありました。
【Q】八王子市においては、災害弔慰金の支給が配偶者になされることとなっておりますが、同性パートナーシップの方も支給の対象となっているのでしょうか。現状を確認させてください。
【A】八王子市の災害弔慰金の支給は「八王子市災害り災者救護条例」で規定されておりますが、同性パートナーシップの方は本条例の支給対象とはなっておりません。
【Q】パートナーシップの方は含まれていないとのことですが、「八王子市災害り災者救護条例」条例を参照しますと、支給の対象者には「配偶者」と記載されております。この配偶者には「事実婚」の関係にある方も含まれるのでしょうか。
【A】本条例において、災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、『災害弔慰金の支給等に関する法律』の第3条第2項を根拠としておりますので、いわゆる「事実婚」の関係にある方も含まれております。
災害弔慰金を支給する遺族について事実婚関係の方も配偶者に含まれるとのお答えでした。
法的には婚姻関係を結んでいないという点では、同性パートナーの方も事実婚と同じ状態のはずです。事実婚関係にあるパートナーが異性であるときは災害弔慰金が受け取れるのであれば、事実婚関係のパートナーが同性であっても受け取れるようにしていくのが自然ではないのかと、私は思います。事実婚関係の相手が異性である場合と同性である場合とで、対応が異なるというのは、不合理ではないでしょうか。
【Q】先ほど示したように、他自治体においては、パートナーシップ関係にある方を支給の対象としている例も見られます。自治体間の格差ともとらえることができます。改めるべきではないでしょうか。
【A】災害弔慰金のような支給順位がある制度では、パートナーシップの方を支給対象に含めることで、支給対象から外れる親族が出てくる可能性があります。慎重な整理が必要であることから、現状自治体の対応も様々であり、国においても検討が続けられているところとなります。今後とも、国や他自治体の状況、社会情勢などを注視してまいります。
退職手当を亡くなった労働者の遺族が受け取る場合に、遺族固有の権利として見なされるのと同様、災害弔慰金においても、遺族固有の権利として考えられるかと思います。先ほどの答弁では、市の職員の退職手当の場合、同居して生計を一にしている同性パートナーの方について、事実婚の方と同じように配偶者として対応するかどうかは、申し出の内容を踏まえ慎重に判断するというお答えでした。個別の事情を踏まえて判断するということで、否定はしませんでした。災害弔慰金の支給についても、個別の事情を踏まえて同性パートナーの方を配偶者として対応していただくよう、要望します。
(2) 性の多様性の尊重に関する条例づくりを
昨年3月26日に犯罪被害者給付金不支給裁定取消請求事件に係る最高裁判決が出され、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」において、給付金の支給対象の遺族として定められている、「婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」に同性パートナーも含まれ得るとの解釈が示されました。
この最高裁判決を受け、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」という文言と同一、または類似の文言を含む各法令の対象に同性パートナーを含むと解釈するか、関係省庁で検討が進められています。今年1月の共生社会担当大臣記者会見によれば、検討の結果、含まれ得るとされた法令は公営住宅法を含め24、更なる検討が必要とされた法令は災害弔慰金の支給等に関する法律を含め130でした。この会見では、更なる検討が必要とされた法令について、最高裁判決を重く受け止め、含まれ得るとされた法令も参考にしながら早期の結論が出るよう検討を加速化していくとの考えが示されました。
国の検討結果を待つだけではなく、条例を定めて実施する主体として、市としてどうしていくのが適切なのか、制度の趣旨や目的を踏まえて検討を進めることも必要ではないかと考えます。その検討を進めるにあたり、市の方針・考え方を示す、性の多様性の尊重に関する条例づくりの必要性について、考えていきたいと思います。
【Q】八王子市では、男女共同参画推進条例の基本理念の中で「誰もが個人としての尊厳を重んじられることにより、性別による差別的取扱いを受けることがなく、その個性及び能力を発揮し、自らの意思により多様な生き方を選択できること」との規定があります。この条例には、性の多様性の尊重や、性自認および性的指向を理由とする差別解消について、盛り込まれているのかどうか、確認いたします。
【A】八王子市男女共同参画推進条例は、あらゆる場面で男女が共に参画できる社会の実現を目的として制定したものです。「性の多様性の尊重」につきましては「男女が共に生きるまち八王子プラン」に基づいて、LGBT相談や、性の多様性を尊重するための意識啓発と情報提供を行っております。
性の多様性の尊重については、男女がともに生きるまち八王子プランに基づいて、相談窓口の設置や、意識啓発や情報提供を行うにとどまっています。つまり、条例には盛り込まれていないと理解しました。
東京都は、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例」の第三条に、性自認および性的指向を理由とする不当な差別の解消を条例の趣旨として定めています。また、同条例の7条の二に、パートナーシップ宣誓制度の実施を定めています。
これまでの議論において、本市では、独自の制度の制定はせず、「東京都パートナーシップ宣誓制度を活用」していくということですが、この東京都パートナーシップ宣誓制度を自分たちのものとして活用していく取組みは、まだまだ弱いと感じています。
すでに導入済みの4業務だけでなく、更なる活用に向けて検討を進めるとしているものの、なかなか進んでいない現状があります。先ほど指摘したように、災害弔慰金においては、東京都パートナーシップ宣誓制度を活用できる自治体がある一方で、本市では活用ができません。また、職員の退職手当についても、同居して生計を一にしている同性パートナーの方について、事実婚の方と同じように配偶者として対応することを否定こそしませんでしたが、個別の事情をみてその時々で判断するとなると、かえってトラブルが生じることになりはしないでしょうか。条例で定めることで、市の執行の安定性も保てるかと思います。
国立市、日野市、町田市などの先進自治体では、性の多様性の尊重や差別解消を盛り込んだ条例をつくり、その条例の理念を踏まえた市独自のパートナーシップ制度を合わせて導入しています。単に制度を導入するだけでなく、性自認や性的指向を理由にした不当な差別のない社会の実現を基本理念として条例に掲げています。
【Q】性の多様性の尊重を尊重することや性自認・性的指向による差別をなくすことを盛り込んだ条例の制定や、その理念を実現する市独自のパートナーシップ制度の創設が本市にも必要と考えますが、市長の考えを伺います。
【A:要旨】八王子市の基本計画である八王子未来デザイン2040では、「一人ひとりが尊重される地域社会の構築」を施策として掲げている。その施策の一つとして、東京都のパートナーシップ宣誓制度を活用した行政サービスに取り組んでおり、引き続き、多様な個性等が尊重される社会意識の醸成に取り組んでいく。
多様な個性等が尊重される社会意識の醸成を図る上でも、多様性の尊重や差別解消が盛り込まれた条例や制度の創設が求められています。
先に挙げた先進自治体では、条例や独自のパートナーシップ制度の構築にあたり、市民委員会を立ち上げたり、当事者の声をきいて反映させたりしています。こうした議論の過程を大切にしてこそ、多様な個性が尊重される社会意識の醸成が図られると考えます。男女共同参画推進条例の制定にあたり、検討会に参加された市民からは、多様な性の尊重も含めたジェンダー平等の視点が必要ではないかとの意見が出されたものの、条例には反映されませんでした。
性自認および性的指向を理由とする不当な差別の解消をなくしていくための、より実効性のある取組を進めるためには、性の多様性を尊重する条例が必要ではないかという思いから、今回質問してまいりました。
改めて、性の多様性の尊重、差別解消にむけた取組みの推進にむけて性の多様性を尊重する条例づくりや市独自のパートナーシップ制度の創設を求めまして、私の一般質問を終わります。