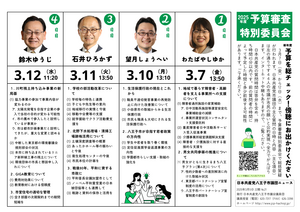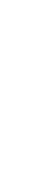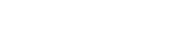2025年第1回定例会本会議|2025年度予算等議案に対する会派代表質疑|2025年3月5日 市川かつひろ
それでは、ただいま上程されております、2025年度八王子市一般会計、各特別会計及び公営企業会計予算並びに関連する議案につきまして、日本共産党八王子市議会議員団を代表して、質疑を行います。
はじめに予算編成の前提となる国の経済見通しと市民生活の実状についての認識についてです。政府の2025年度の経済について「総合経済対策の効果が下支えとなって、賃金上昇が物価上昇を上回り、個人消費が増加するとともに、民間需要主導の経済成長となる」政府の見通しを背景に、予算編成方針では「景気は、一部に足踏みが残るものの、緩やかに回復している」との情勢分析をしています。
しかし、物価の上昇を考慮した実質賃金は1996年をピークに2023年までに年収で74万円も低下しました。暮らしに困難をもたらしたことが内需を冷やし「失われた30年」と言われる経済停滞を生んでいます。そこに、円安を起因とする急激な物価高が市民生活を苦しめています。
総務省が発表した2月の東京都区部消費者物価指数は、価格変動の大きい生鮮食品を除く総合指数が108.5と、前年同月比2.2%上昇となり42か月連続の上昇です。食料品高は続いており、コメ類は77.5%上昇と5か月連続で過去最大の伸びとなりました。
帝国データバンクによると今年1月の主要食品メーカーの値上げはパンを中心に1380品目で22年の同社の調査開始以来、1月としては最多です。厚労省の最新の「23年国民生活基礎調査」で生活意識が「苦しい」とした世帯は59・6%と前年の51・3%から8・3ポイント上昇しました。
暮らしも、経済も、「良くなる」という希望が見えない、深刻な状況にある市民のくらしに対し、「住民福祉の向上」という自治体の本旨を改めて自覚した予算編成と市政の舵取りが必要と考えます。
さて、提案された2025年度予算は、就任から2年目となる しやけ市長のもと、経済成長、人材確保に重点を予算編成としています。予算編成の考え方として―「歳入と歳出の乖離である「ワニの口」を閉じるための予算とする」ことを掲げておられます。「歳入と歳出の乖離である「ワニの口」とは「今後の厳しい財政見通しに対し、持続可能な行財政運営の確保」についての問題意識とみています。また「ワニの口」をどのように閉じていくかの見解ですが、サンセット方式によるゼロベースでの全事業の見直し、人口規模に応じた公共施設の再編など、歳出削減・市内企業の支援とともに、新たな歳入確保につながる企業誘致など、歳入歳出の乖離の解消に取り組む―とのことです。
そこで市長に伺います。
「歳入と歳出の乖離の解消」を大義名分とした行財政運営は、非正規雇用における人件費の削減、福祉の削減は市民サービスの低下につながり、自治体本来がとりくむ「住民福祉の向上」という自治体の本旨に責任をもって応えられるのだろうかと強い懸念を抱くものです。「サンセット方式によるゼロベースでの全事業の見直し」をはかる一方、既存事業と、これから必要とされる新たな市民ニーズに対し、今後どのようにどう応えていくのか、事業見直しの判断基準を伺います。
次に生活保護行政について伺います。
厚生労働省が発表した『国民生活基礎調査』(2023年7月)では、わが国の相対的貧困率(2021年)は15.4%と、経済協力開発機構(OECD)が公表する各国の貧困率の最新値でみると、最悪となっています。
コロナ対応の様々な施策が終わる中、厚生労働省の調査では、去年1年間に全国で生活保護が申請された件数は、速報値で25万5079件と、前の年と比べて1万8123件、率にして7.6%増えました。新型コロナが感染拡大した2020年から4年連続で増加していて、この11年間で最も多くなりました。しかし、生活保護の利用者は増えておらず、昨年11月の被保護者調査では、対前年同月比とくらべて1万4000人減少し、利用者数は約200万人、保護率は1.62%となっています。
貧困と格差が広がるにもかかわらず、生活保護の捕捉率が広がらないのは、申請に来た人を違法に追い返すなど制度へのアクセスの障壁があること、利用者へのスティグマ(社会的烙印)があること、さらに親族への扶養照会があることが要因となっています。また憲法や法律を守ることが使命の自治体が、全国で違法・不適切な言動や運用を繰り返しています。私どもは、研修の不備・不足、そしてケースワーカーなどの職員の不足が慢性化していることを指摘してきました。
会派として1月に小田原市の生活保護行政について視察してまいりました。視察では、「市長のリーダーシップのもと、生活保護行政の改革・改善に全庁が一丸となって取り組んでいったこと」をはじめ、ケースワーカーの配置基準の充足と専門職の拡充、業務の在り方と連動した職員配置の偏在化の見直し、仕事の中で抱えたストレスに対する支援などの取り組みを学びました。
生活保護制度は「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」生存権です。「生活保護はいのちのとりで」として、市長のリーダーシップのもと行政が一丸となって生活保護の運用改善に取り組み、利用する市民にやさしい制度の運用、そして職員にとっても働きやすい、働き甲斐のある生活保護行政へ取り組んでいただきたいと思います。今後の生活保護行政に対する市長のご見解を伺います。
次に国民健康保険について伺います。
東京都は2023-2024年度の医療給付費の伸びを実際よりも大きく見込んだことにより、都内の各自治体の納付金額を増額し、本市においては保険税の大幅値上げがされました。各自治体から納付金の引き上げに反対する意見に対し、都は2023年度決算余剰金約235億円を活用し、納付金の増額を抑制したことにより、2025年度確定係数に基づく都への保険納付金は前年度比で13臆9600万円減少しました。わが会派が指摘した2023年度決算における医療給付費13億7000万円の不用額の問題を事実上、都はこの誤りを認めたものと言えます。
納付金が下がったのですから、本来であれば本市の徴収金額、税率もさがるべきものであります。2025年度確定係数に基づく1人当たり保険料額は昨年度と比較し5951円(前年度比マイナス3.64%)の引き下げになるものです。
しかし本市の保険税は被保険者にそのことが還元されず、全体で新年度も値上げとなり、さらに重い税負担を強いるものとなっています。
2011年には最高時、一般会計からの繰り入れは82億円だったものが、年度ごとに繰り入れの削減が行われ、被保険者へ負担に置き換えられてきました。新年度は繰り入れを史上初めて計上しないとしています。このことは、市が、国民健康保険制度を社会保障制度ということをいわば放棄したといっても過言ではない問題であることを指摘したいと思います。
納付金が下がったもとで、なぜさらなる増税としたのか、また国民健康保険制度は社会保障制度しての認識があるのか、市長の見解を伺います。
次に、介護体制づくりと高齢者福祉について伺います。
昨年4月に国が訪問介護の基本報酬を2~3%削減したことで、人材不足を招き、訪問介護事業所の休廃止が急増しています。
昨年6月時点に厚労省が公開した全国の介護事業所の調査によると、訪問介護事業所ゼロの自治体が97町村、残り1の自治体が277市町村になっていることが明らかになりました。訪問介護が消滅またはその危機にある自治体が全自治体(1741)の5分の1を超えたということです。さらに半年後の12月末には事業所ゼロ自治体が107町村となり深刻な事態となっています。また民間調査会社・東京商工リサーチの調査では訪問介護を主に行う事業者の倒産や休廃業が昨年、過去最高の529社となったことを明らかにしました。
昨年夏までに2つあった事業所がゼロになった長野県・高山村では、介護業界全体の人員不足や国による報酬削減などで疲弊したことが事業所のサービス提供責任者やNPO法人、社会福祉協議会の証言で明らかにされています。
本市の介護事業所支援策として、事業所の収支改善も含めた経営課題解決支援事業を行っています。しかし事業の周知不足をはじめ利用実績は伸び悩んでいると聞いています。
広域で中山間地を抱える新潟県・村上市は長距離の移動や冬の除雪作業など都市部にない困難に加え、それらにかかる時間は、訪問介護基本報酬に実態として含まれないことから、事業所経営は不安定な状況にありました。村上市長の決断で「学校給食や子どもの医療費への独自支援と同じように」国が減らした介護報酬を自治体が支援し介護資源を守っています。
そこで伺います。
介護加算の申請や経営改善など既存制度の枠内にとどまらず、介護事業所の声や実態を把握し、直接的な支援を検討すべきではないかと考えます。また市として、国に対し介護報酬の引き上げをはたらきかけていただきたいと思います。市長のご所見を伺います。
次に「生活を支える補聴器購入費助成」についてです。
これまで、わが会派から「聞こえは人権の問題」として補聴器購入費助成を求める議論を行ってまいりました。「補聴器をつければ以前と同じように聞こえる」わけではなく、きこえは改善されることはあっても、元通りにはなりません。重要なのは購入後の調整で、その期間は数か月から、年単位を要する場合もあります。耳に補聴器をつけることに慣れ、補聴器からのきこえを脳に認識させる訓練が必要で、高い機器を購入しても、慣れる前に使わなくなってしまう方も多いそうです。
足立区では、補聴器購入費助成とともに、補聴器の調整や補助トレーニングの勧めなど「きこえの相談事業」として言語聴覚士による高齢者の聞こえの相談を行っています。
そこで伺います。
高齢者の聞こえのコミュニケーションの機会を確保し、健康で日常生活を送るうえで、利用者の声を聞き、アフターケアなど総合的な対応とともに、本事業のさらなる充実をもとめたいと思います。ご見解を伺います。
次に障害のある人もない人も共に安心して暮らせるまちについて2点伺います。
はじめに障害者福祉施設への家賃補助についてです。
そもそも本市の家賃補助は本来、公が負うべき施設運営を、地域に委ねる形で始まった経過があります。よって行政の都合で「見直し削減」を提起すること自体、行政の責任を果たしているといえるのか、問題であると考えます。
補助金見直しの理由に、市内事業者の経営の安定が図られているといいます。しかし、2023年度の決算審査において、市内の障害者施設で赤字になっている割合が、一昨年度の26%から昨年度42%に上がっていることが明らかになりました。さらに、経営が困難になった原因さえ把握されていません。
そこで伺います。
八王子障害者団体連絡協議会から、市議との懇談会のなかで、「家賃助成がなくなると事業の継続が難しい状況にある」「家賃補助を継続してほしい」との切実な要望を継続していただいています。障害者の家族会が母体となって開設し、今日の障害者支援の基盤を築いてきた事業者にとって、家賃補助をなくすことは、これまで事業所運営を支えてきた家賃補助という「はしご」を外されるくらいの問題であると考えます。
障害者が安心して暮らすことができる社会の実現には継続したサービスの提供であり、その要をなす家賃補助は、見直し削減ではなく継続と充足こそ必要ではありませんか。市長のご見解を伺います。
次に障害者の生活園域と福祉サービスについてです。
日常生活圏域とは、地理的条件や人口、交通事情などを勘案して国ではおおむね30分以内に必要なサービスが提供される区域としています。地域福祉計画では、福祉圏域を、地域住民による地域福祉活動の推進の範囲、また適切な福祉サービスの供給のための範囲としています。しかし、障害者計画においては、圏域に関する規定がなく、障害福祉サービス施設等の地域偏在を招き、日常生活をおくるうえで支障をきたし、改善を求める障害者団体からの要望も寄せられています。
そこで伺います。
「全ての障害者が、必要な支援を受け、社会参加し、地域で、安定し、充実した自立生活ができるまちづくり」をすすめていくうえで、サービス提供を事業者の経営努力に委ねるのではなく、行政のイニシアチブのもと、住み慣れた地域で日常生活が送れるようにしていくことが必要と考えます。市長のご見解を伺います。
次に子どもたちが安心して学べる教育環境について3点伺います。
はじめに、学校体育館空調機の運用についてです。
現在、学校体育館の空調機設置整備が進められ、新年度ですべての学校体育館に設置されることにより、避難所生活の環境改善とともに、学校行事や授業などにも使用できるよう運用を改善していくと聞いています。
2月に会派で「市政学習会」を行いました。児童の保護者から、「体育館に設置されたエアコンは子どもたちに使われないのですか」との発言があり驚きました。児童が通う小学校ホームページの学校日記には、体育館空調工事は2学期末に終了予定と記載があるものの、その後の状況については一切記載がなく、使用されているのかさえわかりません。体育館を使った書き初めの授業や朝礼など寒い時も多く、子どもから「なぜエアコンがあっても使わないのか」とクラスメイトの間で怒っていると児童から聞いたそうです。「学校の主役である子ども達が恩恵を受けていないので、本当に残念です」と保護者は話します。子どもたちに嫌な思いをさせてしまってはならないと思います。
このような事態のうけとめとともに、今後の運用について、教育長のご所見を伺います。
次に部活動改革についてです。
中学校の指導要領では部活の定義を「生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動」として、授業のような教育課程に基づく活動とは異なる教育課程外の活動ではあるが、「学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意すること」としています。
部活動は子どもの人格の形成に大きな役割を果たしてきました。一方で部活の本来の姿を見失い教職員においては、超過勤務や指導の在り方に悩み、子どもにおいても、理不尽な指導に苦しみ、「なぜ部活をやるのか」など疲弊してしまう側面もありました。
本市が行う部活動改革は「学校部活動の再編と地域と連携した活動の拡充」を柱として、「地域の子どもは地域で育てる」仕組みづくりをめざすとしています。外部委託にも施設整備や指導者、子どもの権利、保護者の経済的負担などの問題があります。
そこで伺います。
今後の部活に対する考えとともに、子どもたちの部活に対する思いを聞き、その声を施策に反映させる体制、仕組みについて、教育長のご見解をお聞かせください。
次に不登校対策「つながるプラン」についてです。
本市の不登校児童・生徒は1900人を超えています。会派としてもこの問題を重視し、市内小学校を視察し、学校長から現場の実態をお聞かせいただきました。
別室指導支援員を配置している実践をお聞きしましたが、別室に登校する子どもたち一人ひとりによりそい、ゆっくりと、子どもの歩幅にあわせて取り組んでおられる様子と報告があり、実際こどもが作成した紙芝居には、子どもたちの大きな可能性と、それを引き出していく先生や地域の方々の努力を学びました。
そこで伺います。
本市の不登校総合対策「つながるプラン」ではスクールソーシャルワーカー、心理相談員の増員、不登校担当非常勤教員配置などすすめてきました。不登校児童・生徒と「つながる」には、地域資源や人材の活用と開拓、人の配置こそ必要であると考えます。今後の不登校対策における取り組みの評価と課題について教育長のご見解を伺います。
次にコミュニティバス「はちバス」の活用について伺います。
フランスでは1982年に世界ではじめて「すべての人が同じように移動する権利をもつ」「交通手段選択の自由がある」交通権・移動権を明文化し「国内交通基本法」を制定しました。都市圏や自治体ごとに「交通計画」を住民参加・合意形成でつくり「計画」にもとづいて施策を具体化・実行し、事後評価が実施され「計画は住民のもの」という考え方が貫かれています。
2009年度から2022年度までの乗り合いバスの廃止路線は合計12万1862キロ、うち廃止後代替運行がされない一般路線バスの完全廃止路線は、1万8786キロにも及び、地方だけでなく、都市部でも路線バスの減便、廃止が相次いでいる状況です。
そこで伺います。
2023年5月の地域公共交通活性化協議会では、はちバスの再編にむけた検討が議論され、「駅にはいかない」「路線バスの横糸」となる路線の検討と、「シルバーパスが使えなくなる」ことが議題の俎上にあがっています。
シルバーパスが利用できることは、高齢者の移動権、交通権を保障し、日常生活や様々な社会活動を支え、健康寿命の延伸にもつながる福祉的な視点からも重要です。
「はちバス」の再編にあたっては、住民の地域交通に対するニーズを把握するとともに、はちバスの活用を「住民の交通権・移動権を優先させる」視点でこそ取り組むべきではないでしょうか。地域公共交通に対する市長の考えを伺います。
次にまちづくりについて2点伺います。
はじめに北野下水処理場・清掃工場跡地活用についてです。
2022年9月に北野清掃工場が休炉となったことで、10月よりあったかホールは資源循環部から環境部へ所管が変わり、「北野余熱利用センター」から「北野環境学習センター」へと名称変更とともに、環境教育・学習の拠点として、更なる活動の発展が期待されているところです。2023年6月に「北野下水処理場・清掃工場跡地活用基本構想」が示され、同施設を含む周辺地域の活用条件など検討を進めるとし、現在は各種調査が行われていると聞いています。
そこで伺います。
指定管理期間が終わる2028年以降の同施設の活用については、解体を含め検討されているとのことです。これまでの環境教育・学習の拠点としての機能を縮小させることなく、継続していただきたいと考えます。市長のご見解を伺います。
次に、川町スポーツパーク計画と地域住民への影響についてです。
東京都自然環境保全審議会規制部会では、審議の中で、本計画の事業者は、資産力や適格性、信用性が欠如しており、事実上破綻した計画であることが明らかになりました。また規制部会は、スポーツパークの運営が毎年大きな赤字を出すことから、自然の保護ができる新たな計画を出すことを求めました。しかし、その計画も出されず、審議は長期間にわたってストップしています。
本計画の目的は、本市のスポーツ振興の寄与を目的にサッカー場、野球場、テニスコートなどの建設にありました。しかし、計画地に太陽光パネルを設置する新規事業者がこの計画に参入すると聞いています。スポーツパーク計画という当初の計画目的が、大きく変更することになるのか。本計画から13年になろうとしています。当該計画について、市長のご見解を伺います。
次に防災・減災対策について3点伺います。
はじめに自治体職員への対応についてです。
能登半島地震から1年が経過しましたが、今なお避難所をはじめ困難な状況にあります。被災地の自治体職員は自らも被災者でありながら通常業務と並行して震災対応業務に追われています。本市から22名の職員が被災地へ派遣され、支援活動の報告が行われました。
「しんぶん赤旗」(24年6月20日付)によれば、昨年1月の輪島市職員の時間外勤務は平均97時間でした。時間外勤務の時間が月80時間以上という過労死ラインを超え、誰もが過労死してもおかしくない状況であったことがわかります。さらに震災から4か月が経過しても時間外勤務の平均時間は53時間であり、最大204時間も働いている職員が存在していました。
被災自治体の職員を対象におこなった自治労石川県本部がおこなったアンケート調査では「最も改善を求めることは何ですか」との問いに「人員配置の見直し」が74.6%と最も高く、次いでカスタマーハラスメント対策、休暇の取得環境向上、時間外勤務の削減となっています。
そこで伺います。大規模な災害が発生すると、その直後から自治体職員が殺人的な長時間労働を負い、さらにその困難は一時的ではなく、継続しています。自治体職員が疲弊していれば、復旧・復興はかないません。職員数の増大、労働時間の削減、体調管理など、防災減災対策における自治体職員の育成と体制をどのようにすすめていのか、市長のご見解を伺います。
次に避難所の整備についてです。
避難所の環境は命を左右する問題です。不便な生活から高いストレスにさらされ、災害関連死が後を絶たない状況でもあります。災害関連死の認定事例ではどれも「生活環境の激変による心身に相当の負担」が原因とされています。
災害時における給食センターの活用など温かい食事の提供、眠れる環境の整備、トイレなど「被災者の人権を保障する」視点とともに、避難生活で女性が直面する不安の解消や犯罪防止の観点から、避難所の運営に女性の視点を反映させることも必要です。
そこで伺います。
しやけ市長は、就任直後から、いつ起こるかわからない自然災害の備えとして平時からの安全安心にむけた取り組みが地方自治体に課せられた使命と述べておられます。避難所環境の整備、運営の改善について、市長の見解を伺います。
次に都市インフラの整備についてです。
埼玉県八潮市で道路の交差点が陥没し、トラックが転落した事故から1か月が経過しました。原因は、下水管の老朽化による破損とみられ、復旧とともにトラック運転手の一刻も早い救出が求められます。国土交通省の「下水道管路メンテナンス年報」によると、国内で2022年度末までに整備された管路は、約49万㌔に達しており、そのうち耐用年数の50年を超過した管路は全体の7%にあたる約3万㌔にのぼります。10年後には約9万㌔(約19%)、20年後には約20万㌔(約40%)になる見通しを示しています。2023年度は全国で計68.3㌔で異常がみつかり、点検が完了したのは52%にとどまります。下水道管などが原因の道路陥没は、2022年度だけでも全国で約2600件発生しています。本市は、災害時の幹線となる「緊急輸送道路」など40路線で目視による路面点検を実施し異常がないことを確認し、引き続き、マンホールや下水道管内部の調査を行うと聞いています。
そこで伺います。
住民の安全を守るために老朽インフラ対策は急務です。国に対し予算の拡充と人員の確保をはじめとした要請とともに、今後の調査点検など、下水道事業における管路などのインフラ整備をどう進めていくのか、市長のご見解を伺います。
次に同性パートナーシップ制度について伺います。
国際的にみて我が国のジェンダー政策は遅れているもとで、地方自治体では独自に権利保障を進め、パートナーシップ制度が導入し、行政サービスとの連携も図るなか、制度の人口カバー率は7割を超過しています。自治体独自にパートナーシップ制度の導入をはかることで、性の多様性を尊重し、だれもが安心して暮らしていけるまちへ大きく前進しています。
例えば、同居の子どもを家族認定する「ファミリーシップ宣誓」や県庁職員や市職員について、結婚祝い金や死亡弔慰金の支給、結婚休暇や忌引休暇の取得などの福利厚生、その他にも30を超える事業が実施されています。
そこで伺います。
「性的指向や性自認を理由に困難な状況に置かれることがなく、誰もが安心して暮らしていける」ために、「性の多様性を尊重する」市政運営にむけて、同性パートナーシップ制度の検討を求めるものです。しやけ市長のご見解を伺います。
最後に平和行政の推進について伺います。
日米首脳会談で石破首相は、日本の軍事費を2027年度以降も「抜本的に防衛力を強化していく」と軍拡を誓約し、辺野古への米軍新基地建設を「極めて重要」と強調し、核兵器の使用で相手国を抑え込む「拡大抑止」の「さらなる強化」まで宣言しました。異常な軍拡のしわ寄せは、すでに市民の暮らし、医療、福祉、教育などあらゆる分野に及んでいます。「新しい戦前」という言葉が、今、現実化しようとしている不安・懸念があるもとで、今年は戦後80年の節目を迎えます。
戦争体験の継承とともに、憲法9条を土台に民主主義を守ってきたことの継承も重要です。また市民がつくりあげてきた平和の取り組みや運動を次の世代に引き継ぐことも大切な取り組みであると考えます。2025年度は、多摩地域26市で構成する『平和首長会議東京都多摩地域平和ネットワーク』が開催する平和サミットへの参加をはじめ、「被爆樹木2世を植樹する」と聞いています。戦後80年にあたり、本市の平和行政をどのようにすすめていくのか、市長のご見解を伺います。
以上で、日本共産党八王子市議会議員団の代表質疑を終わります。